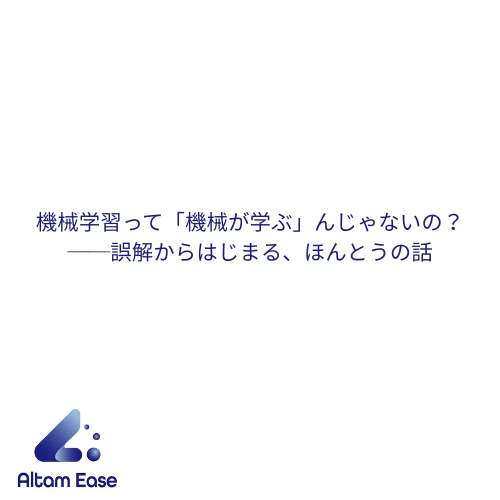
機械学習って「機械が学ぶ」んじゃないの?──誤解からはじまる、ほんとうの話
こんにちは。Altam Easeの本田直輝です。
「機械学習って、AIが自分で賢くなるんでしょ?」
そんなふうに思っていた方、少なくないはずです。かく言う私も、最初はそうでした。
コンピューターが勝手に成長して、勝手に判断して、勝手に未来を切り開いていく。そんなSFっぽい想像が、自然と頭をよぎってしまう。でも実は、“機械が学ぶ”という言葉はちょっとした誤解なんです。
今回は、そんな誤解から始まる「機械学習」の本当の姿を、初心者の方にもわかりやすくお話ししていきます。
「学習している」のは誰?
「学習」という言葉を聞くと、人間のように知識を吸収したり、経験から賢くなったりするイメージがありますよね。でも、機械学習における「学習」は、“ただの計算”です。もう少し正確に言うと、人間が設定した目標に向かって、数式(モデル)の中の“重み”と呼ばれる数値を調整していく作業。それだけなんです。
つまり、AIが自分の意志で勉強しているわけでも、感情や直感を持って進化しているわけでもありません。用意されたルールとデータをもとに、ただ淡々と“最適化”しているだけ。
ではなぜそんな単純な作業が、画像認識や自動運転、翻訳までできてしまうのか?
それは逆に言えば、「人間の作る仕組みがすごすぎる」からに他なりません。
機械学習には「学び方」がある
そんな「計算としての学習」にも、いくつかの種類があります。代表的なものは次の3つ。
教師あり学習──先生が教えてくれる学び方
もっともポピュラーなのが「教師あり学習」。これは名前のとおり、「先生(教師)」がいて、ひとつひとつのデータに「これが正解だよ」と教えてくれる学習方法です。
たとえば、「このメールは迷惑メールか?普通のメールか?」を判断するAIを作る場合、あらかじめ大量のメールに「これは迷惑」「これは普通」とラベルをつけておきます。それを見せながら、「こういう内容だったら迷惑メールになりやすいな」と、AIが法則(パターン)を発見していくのです。
この方法は、データに「正解」が必要なので、事前の準備は大変。でも、そのぶん精度の高い予測が可能になります。
教師なし学習──自分でグループを見つける学び方
一方、「教師なし学習」は、先生がいない世界です。つまり、「正解」がついていないデータを使って、AIが自分でパターンを見つけるという方法。
たとえば、ショッピングサイトのユーザーの行動データを分析して、「このユーザーはこのグループ」「あのユーザーはあのグループ」といった感じで分類する、いわゆる「クラスタリング」と呼ばれる処理がよく使われます。
誰かが答えを教えてくれるわけではありません。でも、何かしら共通点を見つけて、似た者同士をまとめていく。まるでクラス替えの後の中学生が、「あ、この子とは気が合いそうだな」とグループを作っていくような感覚に近いかもしれません。
強化学習──ごほうびで学ぶタイプ
最後に紹介するのが「強化学習」。これはちょっと変わったスタイルで、行動してみて、うまくいったら“報酬”がもらえる、うまくいかなかったら“罰”がある。それを繰り返して、最善の行動を学んでいくという方式です。
強化学習の代表格は、囲碁や将棋、マリオのようなゲームのAI。最初はメチャクチャなプレイをします。でも、「勝ったら100点」「負けたら0点」といったルールの中で、少しずつ“勝ちやすい動き”を学んでいく。
まるでペットをしつけるように、「これをやったらエサをもらえる」という経験を積んで、賢くなっていくわけです。
学ぶのは、あくまで「重み」
ここまで3つの学習方法を紹介しましたが、どの方法も本質的には「モデルの中の数値(重み)を調整しているだけ」です。
猫の写真を見て「これは猫だ」と判断できるのも、マリオが敵をジャンプで避けられるようになるのも、すべては膨大な計算の結果。人間が設計した仕組みに従って、最適な数値を探しているにすぎません。
つまり、「学習している」のは“意志ある存在”ではなく、“数式そのもの”なのです。
まとめ:「機械学習」とは、人間の知恵を計算で動かすもの
機械学習とは、あくまで人間の作ったルールと仕組みの上で、数値的に最適化をしていくプロセスです。
たしかに“機械が学ぶ”ように見えるかもしれません。けれどその裏には、設計者の知恵、教師の手間、報酬の設定…すべて人間の知性が詰まっています。
だからこそ、機械学習を理解する第一歩は、「機械が勝手に学ぶわけじゃない」という認識から始めるべきなのかもしれません。
おわりに
この世界は、言葉ひとつで誤解されやすいことがたくさんあります。「AI」や「機械学習」もその代表格。でも、誤解をほどいてその仕組みを知ると、世界の見え方がガラッと変わります。
もっと深く知りたい方のために、次回は「実際にどうやって画像を分類してるの?」とか「ChatGPTもこの学習法なの?」といった話にも触れていこうと思います。
よろしければフォロー・ブックマークなどしてお待ちください。



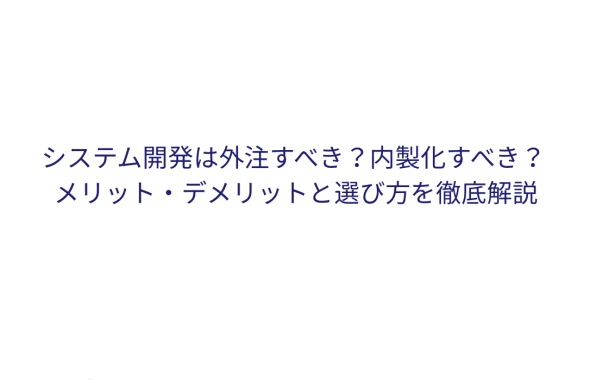
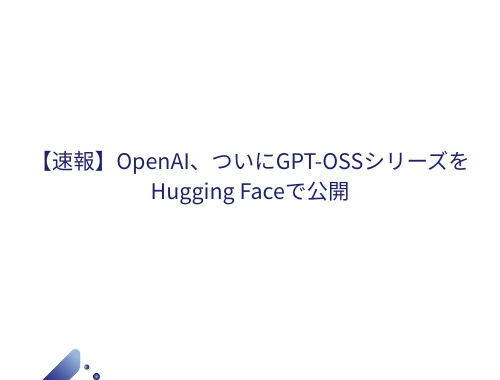
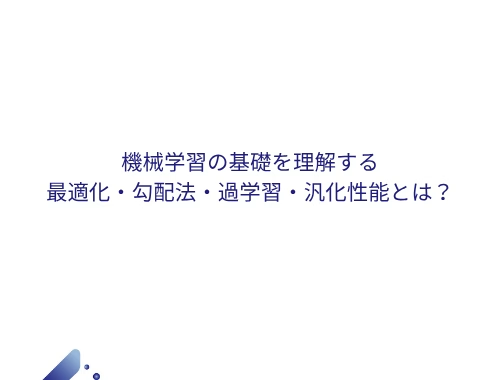
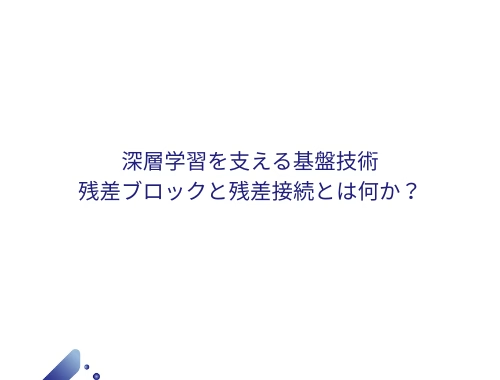
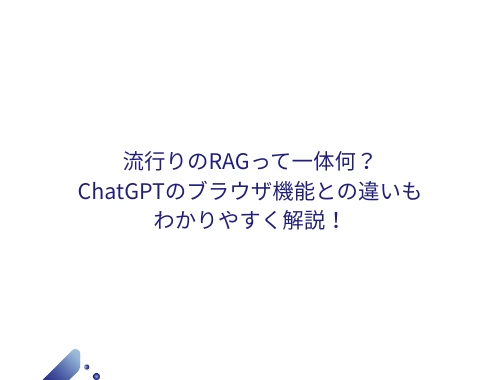
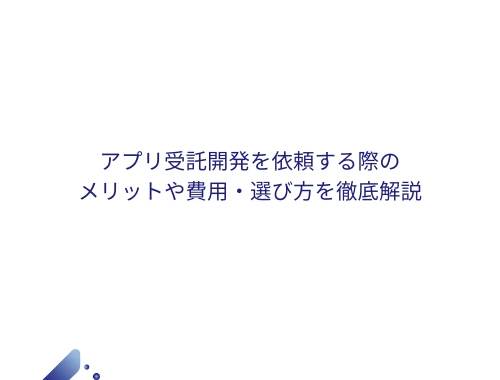
この記事へのコメントはありません。